|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-理由- (1)日本の主力空母4隻に対してアメリカの空母は3隻。しかし、ミッドウェイ島の基地を入れれば運用できる航空機の数では互角。 ( 日本  約282機 VS アメリカ 約282機 VS アメリカ 約310機 ) 約310機 )(2)艦船数全体で比較するとアメリカはわずか三分の一ですが、自国領内の防衛と言う有利な条件だった。 (3)連戦連勝の気の緩んだ日本軍に対して、追詰められたアメリカ軍、兵士の士気はアメリカの方が高かった。 (実際、多くのアメリカ軍パイロットが捨身で戦った) (4)既に空母を運用した飛行機の時代になっていたので、参加していた空母以外の日本の艦船は、あまり意味を持たなかった。 (5)南雲中将と同様にアメリカ側のフレッチャー少将(第17任務部隊)やスプルーアンス少将(第16任務部隊)も航空機の運用は素人だった。 (6)暗号解読により1942年5月22日の時点で、目標がミッドウェイである事や日本艦艇の数、到達日時まで把握していた。 (7)最高決定権を持つ司令官、山本五十六大将、南雲忠一中将、山口多聞少将、阿部弘毅少将、近藤信竹中将らが全員「天中殺」だった。
--- 最高司令官の比較 --- ※企業で言えばCEOに相当 |
|
--24分類法:全般--
Mタイプであった山本は、例えるなら名人的・職人的であり、特定の分野で飛び抜けた才能がある為、軍人にも多いタイプです。
しかし、どう努力しても、そもそもの視野が狭い為、大規模な組織を動かす総司令官には向いていません。事実、山本も自らの実戦指揮能力に疑問を抱いていたとも言われています。実際、Mタイプの場合、経営者の中でも個性の強い、ワンマン社長タイプが多い傾向があります。
しかし、視野の狭い反面奥が深く、集中力は並外れてありますので、山本の場合も全体を纏める総司令官ではなく、専門分野を活かした、一部隊の指揮官として陣頭指揮を行う方が向いていました。
一方のニミッツはKタイプですが、これは大企業の経営者やなどで求められる、大局的な視野の広さを持っており、段取りを考える仕事に適しますので、最も総司令官に向くタイプです。 特徴としては、NタイプやMタイプに比べると集中力が持続しにくく、考える時も行動する時も常に頭を働かせる(悪く言えば雑念が入りやすい)のが特徴です。 これら「才能の領域」の特徴からも、日米の海軍トップはまったく対照的な総司令官だった事が伺えます。
(人事:部下の起用)
ここに両司令官の根本的な考え方の違いが見て取れます。 「下手なところがあればもう一度使う。そうすれば、必ず立派に成しとげるだろう」(山本大将) 「有能な人材を使わないのは不経済だ。しかし、長く使うと弊害が生じる」(ニミッツ大将)
|
ニミッツの発言にある「弊害」とは、固定的な人事における一般的なマイナス面の意味と敵にパターンを読まれない為の両方を指していると思われますが、24分類の要素の一つである「天中殺理論」としても深い意味があり、偶然とは言え、的を突いている気がします。
「天中殺理論」とは簡単に言えば、人間の出番と休みについて認識し、それをうまくコントロールする事を説いています。
どんな有能な人間でも必ず調子のいい時と悪い時が周期的に巡ってきます。 一見すると予測不可能なこの現象を研究し、法則化したのが24分類の要素の一つである「天中殺理論」A〜Fの6タイプなのです。
(実際には、年周期の概念の他にも様々な形態で定義されていますが、一般的には主要6タイプだけでも十分に活用できます。) この「天中殺現象」、個人であればその範囲で済む事ですが、企業のトップや戦時のトップなどの場合は、集団を巻き込んでの大失態にも繋がる事が、このミッドウェイ海戦の検証を見ても実証されています。偶々ミッドウェイだけ?とんでもありません。レイテ沖海戦でも同様の現象が確認されています。(最近の企業で言えば、日産の業績とその役員たちの研究からも確認する事が出来ます。)
さて、日本海軍の人事ですが、日本の山本司令長官(MDタイプ)は人事の偏りを相当注意していたらしく、自分を取り巻く参謀に関しては、敢えて考えの合わない人間を配置して居たようです。実際、参謀長の宇垣纏(KFタイプ)や作戦立案を担当した主席参謀の黒島亀人(KEタイプ)を配置し、大局的な視野で意見やアイディアを出せる人材(Kタイプ)を確保する事で、周囲や軍令部を納得させる事に成功しています。

黒島参謀
Kタイプの参謀たちは、その視野の広さを活かして上司であるMタイプの山本を説得し、意見を封じこめる事が多くなったのです。
事実、主席参謀の黒島(KEタイプ)は、ミッドウェイ海戦前日にキャッチしていたアメリカ機動部隊の動向を、山本が「知らせた方がよい」との意見を遮って、空母「赤城」の南雲に連絡しませんでした。この時、山本は嫌な顔をしてムクれていたと言います。
もし山本ではなく、Kタイプの東郷平八郎(24分類:KF)だったら、自身の判断で決断を下し、黒島の意見など無視して、直ちに南雲艦隊へ連絡していた事でしょう。
 (総司令官に最も相応しい、Kタイプだった東郷平八郎)
(総司令官に最も相応しい、Kタイプだった東郷平八郎)こんな話があります。日露戦争の日本海海戦で2日目の追撃戦の際、ロシアのバルチック艦隊が日本の艦隊に包囲され、午前10時半頃にとうとう降伏旗を掲揚しました。しかし、Kタイプの司令長官東郷平八郎(24分類:KF)は砲撃を止めませんでした。側近の先任参謀 秋山真之(24分類:NF)は進言しました。「長官、敵は降伏いたしました。発砲をやめましょうか?」しかし東郷は黙って敵を睨んだまま、一言も言わない。
「長官、武士の情けであります。発砲をやめてください」 しかし東郷は少しも動ぜず 「ほんに降伏したっとなら、艦をストップさせにゃならん。現に敵は、まだ前進しちょるじゃなかか」 秋山はそれ以上何も言えなかった。 ( 「良い参謀 良くない参謀」より )
この様にKタイプの司令官の場合は自身で大局的な視野によって判断出来るので、そもそも、部下(この場合はNタイプ)を頼りにしておらず、自分で迷うことなく決断が下せます。
話を戻しましょう。24分類の違いは、組織の上下関係があったとしても、結果的に上司の判断まで狂わせる影響力を持っています。
敢えて嫌いなタイプの意見も聞くようにと、ある意味、感を頼りに配慮した山本ですが、本当の自分の欠点を分かっていなかった事が災いして、結果的には配慮で行った人事が、幕僚主導型と言う日本特有の最悪の組織を作り上げてしまいました。
さて、山本の参謀人事と対象的なのは、作戦実行の各部隊の司令官の人事です。驚いた事に全員山本と同じ天中殺タイプのDタイプだったのです。これも偶然にも見えますが、24分類法的には説明のつく事です。
同じ天中殺タイプとは気が合うので、無意識に同タイプを集めた事に他なりません。
山本の人事は、意見やアイディアは幅広く取り入れ、実行部隊には信頼を置ける人物を選んだという、傍目には理想的な人事でしたが、自身も含め個々の性格や個性まではマネージメント出来ておらず、不十分でした。同時に自身がMタイプであったが為に、最も難しい人事だったのです。
ミッドウェイでの大失態のその後ですが、冒頭の発言に在る通り、山本は人事の更迭は行いませんでした。
その結果、天中殺の司令官がそのままソロモン海戦などに参加しており、負け戦が続く事になります。
|
一方のニミッツに関する、Kタイプの司令官の特徴を捉えたエピソードがあります。
日本軍の占領する島のクェゼリン環礁攻略について、ニミッツが将軍たちを集めて意見を求めた時の話です。
一人ひとりに意見を言わせ、全員が作戦に反対し意見を述べ終わると、ニミッツは平然と言いました。 「では諸君、次の目標はクェゼリンだ」将軍たちはそれ以上反対は出来ませんでした。
このエピソードも前述の東郷と同じKタイプの総司令官の特徴をよく捉えています。
Kタイプの場合、そもそも部下の意見は確認程度としてしか捉えておらず、余程違う意見を言わない限り、覆る事はありません。
また、ニミッツやキングに共通しているのは人事に情を一切挟まない事でした。 失敗はもちろん、意にそぐわない結果を出せば直ぐに更迭されました。山本の様なもう一度チャンスをやる事はありませんでした。(これを徹底する事で、結果的に運の無い司令官を自然に排除する事が出来た様でもあります。) また、経歴や士官学校卒業時の成績、自分と合うかどうか等も二の次でした。
起用した司令官が成果を出せるかどうかが焦点であり、そこには年功序列や人間関係のしがらみは存在しなかったのです。
実際、無名だったスプルーアンスを他の将軍を差し置いて急遽、機動部隊の司令官のポストに起用するなど、日本海軍ではありえない人事を合理的に行ったのです。また、「危機に際して必要なのは、もっと攻撃的な司令官だ」との方針の下、士官学校時代の成績のあまり良くなかったハルゼーも起用しています。
この様に、目的を明確化した上で、徹底した合理化を行った事は、ある意味国民性も幸いしていますが、ニミッツの人事システムは大変効果をあげました。しかし、これものニミッツがKタイプでなければ成し得なかったでしょう。
(目的と手段の違い)
ミッドウェイ海戦では作戦そのものに問題が有ったとも言われ、今も尚、議論されて続けていますが、実際の状況は複雑でした。ここでもう一度整理したいと思います。
ここに実際の作戦資料の、「作戦目的」に関する部分だけ抜粋して見ました。
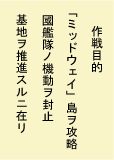
なぜ、南雲はミッドウェイ島攻略にこだわったのか?この作戦資料の意味を正しく解釈して見ましょう。
まず、作戦目的がミッドウェイ島の攻略である事はがハッキリ明記されています。
更にその目的は、アメリカ機動部隊を封止する事となっています。
最後に、ミッドウェイ島に基地を作る事となっています。
さあ、山本の部下である、南雲にとって何が一番重要だったのでしょうか?
それは紛れも無く、ミッドウェイ島の攻略が南雲にとっての最終達成目的であり、一番重要な事でした。 なぜなら、作戦目的の二行目に確実に書かれている以上、ミッドウェイ島の攻略が果たせなければ、作戦自体は失敗した事になり、例え現れたアメリカ空母を全てやっつける事が出来ても、結論としては、事実上、作戦が阻止された形になるからでした。
ちょうど数週間前の珊瑚海海戦で日本は米空母を2隻も撃破したものの、最終目的であったポートモレスビーの攻略を中止に追い込まれた経験があり、その事も南雲の意識に深く焼付いていたと思われます。
実際、2行目が達成出来なければ、必然的に4行目も果たせなくなります。これは、敗北とまで行かなくても、作戦失敗である事は間違いありません。
山本司令長官から命令を受け、作戦行動を行うからには、作戦目的の達成が最重要事項である事は当たり前の事です。
また、一番の焦点となる作戦目的ですが、これを立案する上で、どこにいるのか分からないアメリカ機動部隊を第一目標にする事は不可能でした。
ただでさえ、10万人規模の艦隊を引き連れて太平洋の真ん中まで戦(いくさ)に行くからには、何か確実に得るものがなければなりません。当然、軍令部からの許可が下りることは有り得ませんでした。
従って、第一目標は所在が不確かなアメリカ機動部隊の捜索ではなく、ミッドウェイ島の攻略という、地図の上で確認の出来る具体的な目標になったのです。
さて、ここで「目的」と「手段」について、最確認してみましょう。
部下、南雲の「目的」は既に説明しましたが、山本の目的は何だったのでしょうか?
総司令官である山本の目的は、当然ながら戦争全体の視野で捉え、今回の作戦立案に至っていることもあり、最終目的が南雲とは違っていました。
実は、3行目にある、アメリカ機動部隊の封止が真の目的だったのです。そして、ミッドウェイの攻略はその目的を達成する為の手段に過ぎませんでした。すなわちミッドウェイ占領し基地とした上で、ハワイからアメリカ機動部隊を誘き出し、一気に叩く事がシナリオとして描かれていました。
実際、それをフォローするかの様に、日本を出発する前、作戦を立案した黒島参謀は南雲や草鹿参謀長ら機動部隊の首脳部に対し、万が一アメリカ機動部隊が現れた場合を想定して、半分の航空機は対艦攻撃を準備・待機するようにと、くどい程指示していたとの記録も残っています。
|
南雲が作戦目的の本音と建前をどの程度理解していたかは、資料3の8:20分の決断を見れば分かります。
米空母発見の報告を受けた同じタイミングで帰ってきた第一次攻撃隊から、燃料が少なく直ちに収容の許可を求められ、結果的にそれを許可しています。
実はこの時の判断は源田中佐が行い、南雲はただうなずく事で決定していたのです。源田も戦後の回想で述べています。図上演習なら、迷うことなく敵空母への攻撃を優先させ、味方の損失はやむ得ないと考えただろうが、実戦ととなると生身の人間を相手にするので、ましてや厳しい訓練を見てきたかわいい部下たちに対して非情な決断を取る事は出来なかったと。
源田の判断はさて置き、司令官である南雲がこの決断を下したのは、この作戦の目的と手段が深く理解出来ていなかった事に他なりません。南雲にとっての目的は、飽くまでもミッドウェイ島攻略だったのです。そして、アメリカ機動部隊の封止は、その目的遂行を阻止しようとする機動部隊の排除の意味でしかありませんでした。
この「目的」と「手段」に関する定義については、人格DNAのバックグランドである学問『縦横家』の「軍略」にてハッキリと明記されています。
企業に置き換えて考えて見ましょう。
社長(CEO)の「目的(A)」と「手段(B)」があります。
社員(役員も含む)の「目的(C)」と「手段(D)」があるとしましょう。
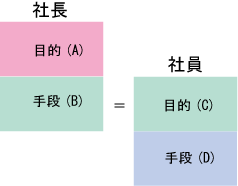
実に(B)=(C)という法則が成り立ちやすいのです。
上司がきちんと部下に対して説明しない限り、(A)=(C)は立場や次元の違いから、 容易には成り立ちません。
【結論】
・真の目的を伝えきれなかったため、南雲長官らの間で誤解が生じた。
 検証3
検証3
--- 実行部隊の司令官を分析 ---(南雲中将と山口少将から学ぶ事)
|
--24分類法:全般--
不運な事に、重要なポストである2人とも天中殺でした。 資料3の07:15の兵装転換の決断は予期せぬ激しい空襲に見舞われた事もあり、いささか仕方ないと思われますが、 08:20頃のやり取りでは、気転を利かせた山口少将(KDタイプ)の進言を、上司である南雲(NDタイプ)は参謀の源田の意見を採用し、却下してしまっています。
24分類法では、Nタイプは石橋を叩いて渡る程の慎重さがあり、ミスが少なく与えられた仕事を集中力を持って取り込めるタイプと定義されていますが、その反面、臨機応変に決断を下し対応する事が不得手ともされています。
それに対し、Kタイプの山口は危機に際して臨機応変に自ら決断を下し、的確に優先順位を判断できるので、リスクを伴っても、チャンスを逃さない積極性がありました。実際「甲乙付けがたい場合は、危険と分っていても積極策を取る」との発言の元、日頃からそのポリシーを貫いていました。
--24分類法:仕事の関係--
|
山口少将は南雲中将の決断が遅く「このままじゃ駄目だ!」と空母「飛龍」の艦橋でイライラしていたエピソードがあります。
ズバリKタイプにとってNタイプの上司は仕事がやりにくくなります。なお、逆の場合はあまり表面化しません。
基本的に才能の領域に違いがあると、お互いの発想や考え方の基準が合わず理解できません。よって思い込みから誤解を招く危険があります。それが上司との関係であるなら、出世にも影響が出ます。
「Kタイプ」は(Hタイプも)根本的に集中力が持続出来ないタイプです。それは頭の良し悪しではなく、能力の違いです。
人と話しながらでも他の事を考えたり、行動中に思考や雑念が入り安く、ある意味特殊な才能です。また一方で、他のタイプに比べて物事を考える際の視野が広く結果としてバランスの取れた考え方が出来ます。優れた経営者や司令官にKタイプが多いのはその為です。
|
「Nタイプ」は基本的に集中力の持続が半端でなく、試験勉強などで有利になります。 実際、当時海軍の出世の順番は卒業時の成績が一生付いて回るやり方だったので、試験に強いNタイプの司令官が多かったのも納得できます。(集中力という点ではMタイプも同様)
また、アメリカ陸軍のダグラス・マッカーサー元帥(24分類:NA)は陸軍士官学校の在学中の平均点が史上脅威の98.14点であった事実もあります。並外れた集中力であった事が伺えます。
Nタイプでもう一つ言える特徴は、慎重すぎる為、自分自身の判断で物の良し悪しを判断できない傾向があります。例えば皆が認める物は認め、少数しか認めない物は認めないといった具合です。 (知名度のあるブランド物などはアッサリ認める)
この事からNタイプは集団を好み、グループ形成によって活躍する人が多く見受けられます。
(フレッシャー少将とスプルーアンス少将から学ぶ事)
|
--24分類法:全般--
MAタイプのフレッチャーは一つ前の珊瑚海海戦で空母運用の経験があった事もあり、ミッドウェイ海戦ではスプルーアンスと同じ少将でありながら作戦全体の総指揮を命じられています。しかし、既に2隻の空母の損失をプレッシャーに感じていた為か、自身の第17任務部隊以外は実質スプルーアンスに指揮権を任せてしまっています。
フレッチャーの属するAタイプは目上部分の欠落により、目下、部下運は良いが上司運がありません。目上に対しては弱点を持つことになります。ですから、このタイプは目上に関わらない方が良く、自らが長の座にあって目下を育てるのに向きます。後に上司であるアーネスト・キング元帥に嫌われ、更迭された経緯も理解出来ます。
実際、企業の経営者でもAタイプは創業者に多いのはその為です。 フレッチャーの場合は更にMの才能領域が加わっています。これは社会性が薄れ、自分本位の考え方を優先させる傾向が強い事を意味しています。我慢強いが、視野の狭い変わり者で、基本的には大組織のリーダーシップは向いていません。単独部署が良好です。
一方のスプルーアンスの属するFタイプの精神面は、他の天中殺タイプと異なり、環境に左右されやすいものを持ちます。 中庸が保ち難く,現実性に流されると超現実性の中に生きる事になり、精神性に流されると現実的な処世術が全く整わない人間性を作り出します。 これは「中央の欠落」によって精神と現実のバランスが保てない事に起因しています。
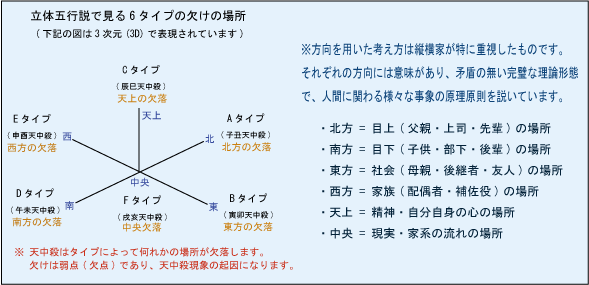
所で、後にニミッツはこのスプルーアンスとハルゼーの両将軍を交互に使い分け、対日戦に効果を上げた事実が残っていますが、そもそも二人は性格が正反対だったとの記録も残っています。 彼らは同じKタイプの才能領域を持つ間柄であり、24分類法だけでは性格の固有の特徴を把握する事が出来ません。
ここで登場するのが、人格DNAの「ポジション図」となります。
|
ここでポジション図について少しだけご紹介しましょう。
簡単に言うなればハルゼーの場合はポジション図の中心にMH(車騎)を保有しており、一方のスプルーアンスは中心にFS(調舒)を保有していた事が大きな性格(人格)の違いになって現れています。
MH(車騎)の大まかな意味・・・行動力、直情、短気、正直
FS(調舒)の大まかな意味・・・反骨、芸術、感性、孤独
一般的にMH(車騎)持っている軍人の方が、戦場では勇敢な活躍を見せるケースが多く、実際に軍人のDNAにはポジション図の場所に限らず、MH(車騎)を保有している人物が多いのも事実です(フレッチャーの場合はSO(南)の位置にMH(車騎)を保有)。
一方のスプルーアンスのFS(調舒)も昔からこれを保有している将軍は、予測不可能な動きをする事で恐れられており、司令官として相応しかったと想像できます。因みにMH(車騎)とFS(調舒)そして知恵を意味するWS(玉堂)の3つを保有していた山口多聞少将が、如何に怖い将軍であった事か想像頂けると思います。
人格DNAのポジション図に関しては今後も詳しく特集したいと思います。
--24分類法:仕事の関係--
資料3の07:02頃にスプルーアンスは予想海域へ向けいち早く攻撃隊を発艦させていますが、この案を進言したのは参謀長のブローニング大佐(24分類:KC)です。 もし彼の進言が無ければ大勝利は難しかったかも知れません(スプルーアンスは当初9:00頃の発艦を予定していた)。ブローニングはハルゼー直属の部下であり、ハルゼー仕込みの即断即決という性格から見ても、かなり性質が似ていると思われますが、偶然にも上司ハルゼー同じKCタイプとなっています。 このKFが上司(スプルーアンス)で、KCが部下(ブローニング)の場合はどのような関係を意味するのか24分類法で見てみましょう。
KFタイプは上昇志向が強いのですが、現実社会において、目的や目標をつかみにくい面を持ち、理解者を得る事が少ないのが特徴です。
一方のKCタイプは現実直視を優先させるので、人生の、或いは仕事においてのより具体的な方向を定める役割を持っています。
ビジネスパートナー関係であれば、CタイプはFタイプに現実直視の力を与える為、上昇度合いが遅くなりますが、 お互いが、KCにとって精神の利があり、KFにとっては現実の利で、欠点を補い合う形になります。
お互いを理解するのに時間がかかりますが、欠点を許しあう関係となり、傍目には厳しさのない間柄にみえます。
|
ここで24分類法の同一タイプであった場合のケースとして、KCタイプの上司(ハルゼー)とKCタイプの部下(ブローニング)の関係を見てみましょう。
同一天中殺(Cタイプ)による、運命バランスの偏りとなります。Cタイプの特徴である激しい気質と、思い通りに人生を歩もうとする傾向があるのに対し、それらの現象が倍加して、拍車が掛かる事になります。 例えば、結婚関係などにおいても波乱動乱が強くなる事を意味しています。つまり理性、知性というより、理屈抜きになり、この結びつきは、諸々の苦難に対して超人的な力を発揮し、 不安、恐れという情性が消滅してしまいます。
例として、探検のための旅行隊を編成したり、未踏の地に足を踏み入れたりという状況の中では、余人が成しえない事を達成させる人間関系となります。
何しろ運命のバランスが偏ることになるため、右か左か善か悪かとなり、中間が消滅してしまうのです。(Dタイプの上級指揮官が多かった日本海軍も同様)
このCタイプ同士の者が、相い争うことになれば、相手が倒れるまで戦いの連続となります。
史実では病気で入院する事になったハルゼーがスプルーアンスを代理に指名し、ブローニングを含める参謀たちをそのままスプルーアンスに使わせる事になりましたが、 これはハルゼーの意思が引き継がれる事を意味しており、結果的にはブローニングがハルゼーの分身として役目を果たす事になりました。
このことは24分類法で同タイプの分類に属する場合、上下関係において自分の分身の役目が果たせる事とされている所以です。
 検証4
検証4
--- 不運 ---敗因の一つと考えられている不運な出来事は、全て「天中殺」の司令官が関わっており、
それとは対照的にアメリカ側では、この作戦のキーパーソンとなる司令官で「天中殺」が巡っていた人物はいません。
|
※太字は天中殺だった人物
1.作戦前日の現地日付 6月3日の時点で、後方の主力部隊はミッドウェイ島の北方からのアメリカ空母らしき信号をキャッチしていたが、
南雲艦隊には連絡をしなかった。
司令長官の山本は直ぐに空母「赤城」に連絡する様に助言するが、この作戦の考案者である黒島亀人 先任参謀(24分類:KE)がこれを
遮った。 草鹿参謀らには出発前に十分警戒する旨は伝えてあるので心配は要らない、むしろ無闇に無線を使用して、アメリカ側に傍受
される方が危険だと言うのが黒島の意見だった。

2.南雲忠一 中将の信頼する航空部隊総指揮官であった淵田美津雄 中佐(24分類:KA) が急性盲腸の為、作戦に参加出来ず、
友永丈市 大尉(31歳)(24分類:KE)が代理する事になる。
 ->代理
->代理
※淵田中佐は真珠湾攻撃でも航空部隊の総指揮官を務めた。
3.同じく、南雲忠一 中将の信頼する源田実 中佐 作戦参謀(24分類:KE)はインフルエンザで体調不良。

※一部の兵員たちの間では、南雲艦隊の事を源田艦隊と呼んだ程の影の実力者だった。
4.後方の主力部隊に乗船していた山本司令長官は、腹痛による体調不良の為に寝込んでいた。(回虫が腸内に巣を作ったのが原因)
・6月4日には、気分転換に将棋をしていた説もある
5.6月4日、支援部隊 阿部弘毅 少将直率の重巡洋艦「利根」のカタパルトが故障の為、偵察エリアへの到達が30分遅れた。
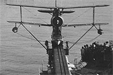
・カタパルト故障の原因は単純な部品欠損であり、整備不良によるもの。
・この事がアメリカ艦隊発見の報告が遅れる原因になる。
・重巡洋艦「利根」の艦長である、岡田為次 大佐(24分類:KC)の監督不行届。天中殺中の1941年9月10日、艦長に着任している。
6.6月4日、支援部隊 阿部弘毅 少将直率の重巡洋艦「筑摩」の偵察機が雲の為、アメリカ艦隊を発見出来ず。
・雲の下にはアメリカ機動部隊(第17任務部隊)が航行していた
7.6月4日、警戒隊の駆逐艦「嵐」渡辺保正 中佐(24分類:KB)が付近に潜伏していたブロックマン少佐(24分類:KA)の潜水艦(SS-168)の
追跡を行い、本隊に全速力で戻る際、上空を捜索していたマクラスキー少佐率いる米軍機に後をつけられ、南雲艦隊の居場所が知られ
てしまう。 実際、エンタープライズ爆撃機隊のマクラスキー少佐(24分類:KA)は燃料不足で引き返すところだった。


8.6月4日、第2航空戦隊山口多聞 少将直率の空母「蒼龍」から飛立った偵察機の無線機が故障した為に役目を果たせず。
・唯一残った「飛龍」に帰艦後、口頭にてアメリカ空母3隻の存在を報告。
 検証5
検証5
--- 勝つための24分類法 ---分類とは複数の事物の性質や属性を調べ、類似性や系統に沿って、選り分ける行為です。人間は花の種類を分類し、その特徴を知ることで、育てて楽しむことが出来ます。また、犬の種類を分類し、その性質を知ることで、飼う楽しみと癒しを求めることが出来ます。
しかし、その人間が人間関係に悩むのは、肝心の人間の内面的は特性を理解していないためです。
24分類法とは人格DNA分析による内面的な特性に基づき、人間を24種類に分類した当サイトのオリジナルの人間分類法です。
分類は多すぎると複雑になり、少なすぎると正確さを欠くことになりますが、24分類法は適切な必要最小限の分類法です。また、横4分類、縦6分類の表に配置することで、違いを視覚的にも知ることができます。
|
天中殺とは人間の運気のバイオリズムであり、誰もが経験する周期的な不調(スランプ)の法則を研究したものでした。 それにより、どの天中殺をもった将軍が攻めて来るかで、相手の状態か予測できましたし、こちらの指揮官の出番を決める重要な要素となりました。これは「軍略」が組織のトップの「予測・対処・準備」の学問であった所以です。
古今東西を問わず、人間は経験的に本人の実力とは別に運が味方するときと味方しないときがあることを知っています。しかし、占い的な軽いものではなく、先人が命がけで探求した東洋の自然思想に基づいた人間界の法則は現代でも「孫子の兵法」以上に充分活用できます。
当人格DNAサイトの24分類の6タイプ(A〜Fタイプ)はこの天中殺分析を活用しており、会社の重要な商談の責任者を決めるなど社員の出番の時期を判断する要素になります。
実際にミッドウエイ海戦に関わった日米の司令官(参謀を含む)を当サイトの24分類の6タイプの天中殺の分類で見ると日本海軍には本来は出番でない指揮官が多いことが分かります。(D−タイプ)
これは同タイプの人の相性が合うため、トップが無意識に同タイプの人を集める傾向があることが原因しており、偏った人事の悪い例の典型と考えられます。
下の表はミッドウェイ海戦に関わった日米の重要人物と6タイプの天中殺(バイオリズム)A〜Fと才能の領域K,N,H,Mを表した「24分類法」です。

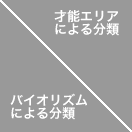 |
K-タイプ ・個人才能で個人で実行できる才能 ・行動中に思考が入り集中でき難い ・現実離れした才能 その他 |
N-タイプ ・個人才能で個人で実行できる才能 ・行動中に思考が入らず集中できる ・日常生活に近い才能 その他 |
H-タイプ ・集団才能で相手が必要な才能 ・行動中に思考が入り集中でき難い ・日常生活に密着した才能 その他 |
M-タイプ ・集団才能で相手が必要な才能 ・行動中に思考が入らず集中できる ・日常生活の中で偏った才能 その他 |
| A−タイプ (1936〜1937年は天中殺) ・自立心・独立心が強く、創業者タイプ。 〔天中殺の特徴〕 |
KA 草鹿龍之介 少将(参謀長) 木村進 少将 |
NA |
HA 小松輝久 中将(★★) |
MA フランク・J・フレッチャー 少将 |
| B-タイプ (1938〜1939年は天中殺) ・ダイナミックでパワフルで自分の人生はj自分で切り開くタイプ。 〔天中殺の特徴〕 |
KB アーネスト・キング 元帥(★★★★) チェスター・ニミッツ 大将(★★★) 高須四郎 中将(★★) 西村祥治 少将 |
NB ハロルド・シャノン海兵中佐 |
HB |
MB |
| C−タイプ (1940〜1941年は天中殺) ・破天荒でアウトロー、現実的なリアリストタイプ。 〔天中殺の特徴〕 |
KC ウィリアム・ハルゼー 中将(★★)入院 マイルズ・ブローニング 大佐(参謀長) |
NC |
HC |
MC |
| D−タイプ (1942〜1943年は天中殺) ・アンカー的な役割を担う頼りになるタイプ。 〔天中殺の特徴〕 |
KD(天中殺) 山口多聞 少将 近藤信竹 中将(★★) |
ND(天中殺) 南雲忠一 中将(★★) 阿部弘毅 中将(★★) 白石万隆 少将(参謀長) |
HD(天中殺) ロバート・H・イングリッシュ 少将 |
MD(天中殺) 田中頼三 少将 山本五十六 大将(★★★) |
| E−タイプ (1944〜1945年は天中殺) ・リーダーの素質を持ち,仲間と経済に恵まれるタイプ。 〔天中殺の特徴〕 |
KE 東條 英機 (内閣総理大臣) 黒島亀人 少将(主席参謀) 源田実 中佐(作戦参謀) |
NE |
HE |
ME 栗田健男 中将(★★) |
| F-タイプ (1946〜1947年は天中殺) ・一度決めた事は険しくても自力で乗り越え頂上に立つカリスマタイプ。 〔天中殺の特徴〕 |
KF フランクリン・ルーズベルト 大統領 宇垣纏 少将(参謀長) レイモンド・スプルーアンス少将 藤田類太郎 少将 三川軍一 中将(★★) |
NF |
HF |
MF |
|
|
あなたの家族や仲間の24分類を確認してみよう!

--- 24分類法をビジネスへ生かす ---
日本海軍の人事管理体制では公平さと適材適所をうたいながらも、人間の好調・不調の特性についてまでの注意が行き届いていませんでした。 いくら優秀なスタッフを揃えても、この特性によってお互いが影響され、組織の機能までもが影響を及ぼすとは誰も気付いていませんでした。
あれから65年経った日本の企業はどうでしょう。未だに手の付けられていない領域ではないでしょうか?
24分類法は今まで感に頼ってきた人材配置を、理論化された裏づけによって、より正確に把握できます。また、配置のバランスを確認する事で、ミッドウェイのような予期せぬ敗北の可能性を、事前に予知し、最悪の事態を回避することが出来ます。
--歴史の失敗から学ぶ為に--
時々、他人の分析には興味が無いと言われる方もおられますが、実際には自分の分析だけを見てもあまり意味がありません。人間は一人で生きているのではなく、必ず家族や学校、会社などのどこかに所属しており、互いの存在を影響し合いながら生活しています。
自分を知るだけでなく、自分を取り巻く人間(環境)も知る事で、初めて自分の位置が分り、どうすべきかの予知学へ繋がります。
では、相手をどの程度まで知る必要があるのでしょうか?
それは目的によって違ってきます。職場やグループなど、多くの場合は人間関係を知るだけで十分なので、人の深い人生まで知る必要はありません。当サイトの提唱する24分類法で知りえる範囲で十分なのです。
さて、当サイトの取り上げる歴史上の人物ですが、彼らの人生を研究しプロファイリングする事は、自分の未来を予測する為の判断材料になり、大変有益な情報です。「賢者は歴史に学び、偶者は経験に学ぶ」という言葉がありますが、歴史に学ぶ事は、先人の知恵を活かし同じ過ちを犯さない為の意味のある行為であり、結局は勝者への近道なのです。
--24分類を正しく理解する--
6分類と4分類は別々に理解することが重要です。
6分類では仕事や家庭との係わり方などがわかります。また、掛けあわせる事で相性も分ります。
4分類では才能の中身ではなく才能の所在と思考法がわかります。
24分類法の原理原則を正しく理解し、実行すれば組織の弱点は無くなります。
<バイオリズムの6分類について>
Aタイプの意味
Bタイプの意味
Cタイプの意味
Dタイプの意味
Eタイプの意味
Fタイプの意味
<才能タイプの4分類について>
Kタイプの意味
Nタイプの意味
Hタイプの意味
Mタイプの意味
--参考文献--
・ウィキぺディア(Wikipedia)
・World War II Database
・「指揮官とな何か」 吉田俊雄 光人社NF文庫
・「良い参謀、良くない参謀」 吉田俊雄 光人社NF文庫
・「戦場の名言」 草思社
・「昭和の海軍」文藝春秋
・「帝国海軍vs米国海軍」文藝春秋
・「日米空母決戦ミッドウェー」Gakken
・「歴史群像 バトル・オブ・ミッドウェイ」白石光 Gakken
・「日本海軍指揮官列伝」宝島社
・「太平洋戦争"戦闘分析"読本」宝島社
※掲載の記事・図表などの無断転載を禁止します
|

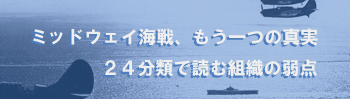
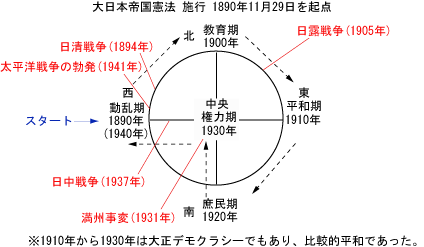
 資料1
資料1 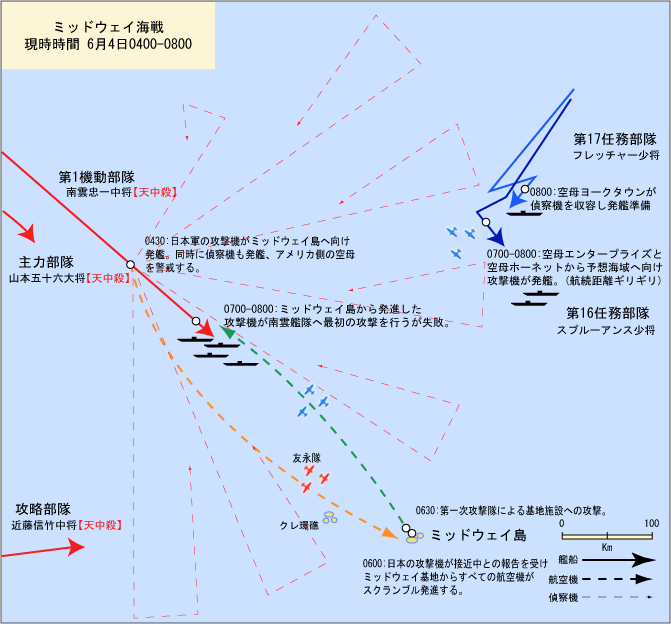


 (マッカーサーの個性の強さに、やや引き気味のニミッツ)
(マッカーサーの個性の強さに、やや引き気味のニミッツ)




